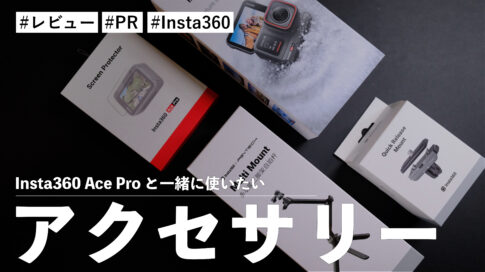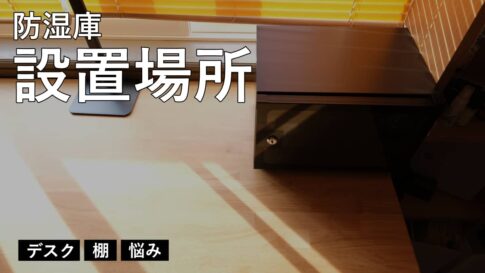念願のカメラ2台持ち。自宅用としてX-H2、外出用としてX-E5といった形で使い分けをしている。今まではX-H2の1台運用で、X-E5を導入したことによりX-H2を手に取ると「X-H2はいいカメラなんだよな」と思う瞬間が多々ある。
2022年に発売したX-H2を”いいカメラなんだよな”と思う瞬間を5選まとめました。X-H2を愛用している同士やこれから購入検討されている方はぜひ最後まで読み進めてもらえると幸いだ。
ではいってみよう!
・自身のご褒美に FUJIFILM X-H2 を購入しました。オーバースペックですが所有欲を満たしてくれるカメラです
Contents
X-H2もいいカメラなんだよなと思う瞬間5選
その1:しっかり握れるグリップ

X-E5を使ってからX-H2を使うとすげー感じるのが、このしっかりと握れるグリップだ。僕の手はかなり大きめなんだけど、しっかりと手全体を使って握ることができる。カメラのグリップを握ると高揚感というか、「あーこれから撮影をするんだな」という気持ちが高まっていく。
しっかりと握ることで、カメラを落っことす心配もないですしね。
X-H2の深いグリップは本当に好み。
その2:モードダイヤルが便利

わりと使っているのがモードダイヤル。基本はブログ用の写真撮影にと”M”にしているが、デスク写真を撮影したり、動画に夜間撮影となるとカチカチとモードダイヤルを回して設定を一気に変えている。
C1〜C7と設定を保存する数が多いものの、僕はC4くらいまでを設定。ちょっとずつ設定を増やして楽しんでいるところだ。
よく使う設定をどこに設定しようかな?と考えながらカメラの設定をいじくり回すのは楽しい。
その3:大きいレンズでもバランスがよい

X-E5に大きめのレンズを装着すると、どうもレンズの方が大きくてバランスが非常に悪いが、X-H2ならある程度大きめのレンズでもバランスが良い。
先にお話した深いグリップのおかげでカメラ自体を持ちやすいし、見た目のバランスも非常によく撮影がしやすい。
ズームや望遠レンズを使うのであれば、X-H2のようなカメラが使いやすいだろう。
ちなみに大きいレンズでなくパンケーキレンズのような小型レンズでもわりと似合うので、気になる方はぜひ試してみるといいだろう。
その4:防水防塵がある安心感

これからの時期により活躍するのが防水防塵性能。これX-E5には搭載していないんですよね、なので冬の北海道だと外に持ち出すのが少し怖い。代わりにこの寒い時期はX-H2が活躍するんじゃないかと思っている。
持ち運び用にX-E5を購入したけど、無理やり持ち出して壊すのはまた違うので、防水防塵を搭載しているX-H2を使うのが間違いないし安心感もある。
ひとつ気がかりなのは防水防塵性能ってのは年々弱まったり劣化することはないのか?ってことぐらい。
それでも防水防塵がないカメラよりは、防水防塵があるカメラのほうが安心。
その5:操作性が好み

2年以上も毎日手にとって撮影しているせいか、身体がもうX-H2の操作性に完全に慣れきってしまっているところがある。各種ボタンや操作スティックの位置など自然と操作できるようになった。
もう慣れたが同じブランドのカメラであるX-E5はまた違ったボタン配置なので、慣れるまでに時間がかかった。それでも操作性はX-H2の方が好みである。
X-H2はX-E5と比べるとカメラサイズは大きいと感じる反面、操作性のしやすいさも考えられているので、個人的には好みです。
まとめ

こんな感じで”X-E5を使っているとX-H2もいいカメラなんだよなと思う瞬間5選”のお話を終えたいと思う。
X-E5を導入したからこそX-H2の良さがまた際立っているなと感じております。写真撮影するのも好きだけど機材も好きなんだなと感じました。
よかったらあなたの愛用カメラが何か教えて下さいね!
では本日はこのへんで。
最後までお読みいただきありがとうございます。
また明日の記事でお会いしましょう!